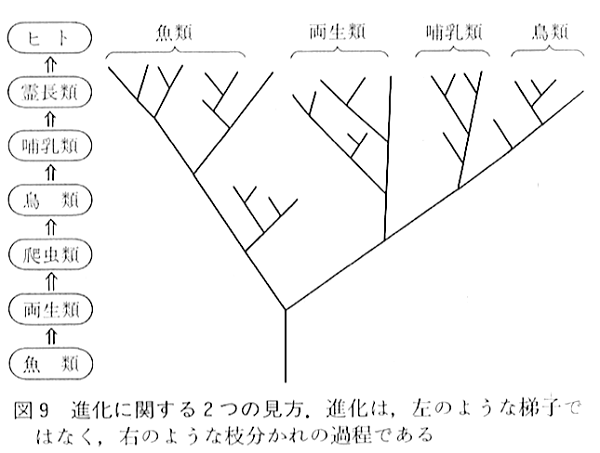1623 スイスのギャスパール・ボアン、『植物対照図表』の一部で二名法を採用。
1686 イングランドのジョン・レイ、『植物誌』で種の概念を発表する。
1694 フランスのジョゼフ・ツルヌフォール、『基礎植物学』で種の上に属、目、網を立てる。
1735-59 スウェーデンのカール・リンネ、『自然の体系』で生物の分類を体系化した。二名法を本格的に採用し、分類学の祖と言われるようになる。
1802 イギリスのウィリアム・ペイリー、『自然神学』でデザイン論を発表。
1809 フランスのジャン=バティスト・ラマルク、『動物の哲学』で獲得形質の遺伝による進化論を発表。
1844 スコットランドのロバート・チェンバース、匿名で『創造の自然史の痕跡』を出版。進化論が注目を集める。
1858 イングランドのアルフレッド・ラッセル・ウォレスとチャールズ・ダーウィンの共同論文を発表。自然選択による進化論を世に出すが、あまり注目されなかった。
1859 ダーウィンの『種の起源』が出版される。注目を集める。
1861 フランスのルイ・パスツール、『自然発生説の検討』を著し、従来の「生命の自然発生説」を否定。
1865 オーストリア帝国のグレゴール・ヨハン・メンデル、『植物雑種に関する研究』を発表。発表当時は反響がなかったが、後世に「メンデルの(遺伝の)法則」として有名になる。
1940年代 ネオダーウィニズム(総合説)が成立。
1968 遺伝子の「分子進化の中立説」をNatureに発表。
スウェーデンの博物学者カール・リンネ(Carl von Linné 1707-1778)は『自然の体系』(1735)を著し、生物の分類を体系化した。現在の分類も彼の体系の改良されたものだ。リンネは分類学の祖と言われている。
以下のような功績により、「分類学の父」と称される。
・それまでに知られていた動植物についての情報を整理して分類表を作り、その著書『自然の体系』(Systema Naturae、1735年)において、生物分類を体系化した。その際、それぞれの種の特徴を記述し、類似する生物との相違点を記した。これにより、近代的分類学がはじめて創始された。
・生物の学名を、属名と種小名の2語のラテン語で表す二名法(または二命名法)を体系づけた。ラテン語は「西洋の漢文」であり、生物の学名を2語のラテン語に制限することで、学名が体系化されるとともに、その記述が簡潔になった。現在の生物の学名は、リンネの考え方に従う形で、国際的な命名規約[2]に基づいて決定されている。
・分類の基本単位である種のほかに、綱、目、属という上位の分類単位を設け、それらを階層的に位置づけた。後世の分類学者たちがこの分類階級をさらに発展させ、現代おこなわれているような精緻な階層構造を作り上げた。
出典:カール・フォン・リンネ<wikipedia
リンネ以前に既に膨大な動植物のデータが西欧に集積されていた。そして分類方法をどうすべきかも案は出されてきた。
自然界のさまざまな存在を収集して命名し、体系化を試みた博物学者は、リンネが最初ではなかった。古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、動物を「無血動物」と「有血動物」に分類した。16世紀のドイツの植物学者レオンハルト・フックスは、500種類の植物をアルファベット順に並べて解説した。英国のジョン・レイは、1686年に発表した『植物誌』で「種」という概念の確立に貢献した。レイと同時代に活躍したフランスの植物学者ジョゼフ・ピトン・ド・トゥルヌフォールは、花や実といった部位の形を基準にして、世界の植物を700あまりの種類に分類した。
上に名前は出ていないが、初めて二名法を公表したのはギャスパール・ボアン(Gaspard Bauhinまたは Caspar Bauhin、1560年-1624年)だった(二名法については後述)。『植物対照図表』(Pinax Pinax theatri botanici、1623)の中の多くの植物の名前に二名法を採用した。この二名法は属と種を使って表した*1が、ボアンの頃の属や種は近代のそれとは違う独自のものだったようだ。
種の概念を初めて確立したのはジョン・レイ(1627-1705)の『植物誌』(Historia generalis plantarum 、1686)。レイの定義はいわゆる生物学的種だった。つまり「同地域に分布する生物集団が自然条件下で交配し、子孫を残すならば、それは同一の種とみなす」というもの。
トゥルヌフォール(ツルヌフォール、1656-1708)は属・目・網の分類を確立した。彼が考案した分類は現在の分類学に受け継がれている*2。
リンネはこうした伝統から出発し、その伝統を越えていった。1735年に刊行された『自然の体系』は他に類を見ない特異な書物で、二つ折りにされたページが十数ページ続く大型本だった。リンネはその中で、自然界を構成すると考えていた三つの世界、植物界、動物界、鉱物界に存在するすべてのものを分類する方法を概説している。[中略]
リンネの命名法も、科学の発展に貢献した。新種の植物が次々に発見されるようになると、種の分類と同様に、命名法にも問題が出てきた。“リンネ以前”は、形容詞や参考情報を延々と書き連ねる命名法しかなかったので、ひどく使いにくいものだった。そこでリンネは『植物の種』という著作で、植物の属と種の名前だけをラテン語で記述する二名法を確立した。1758~59年に大型の2巻本として刊行された『自然の体系』第10版では、二名法を植物だけでなく動物にも適用した。こうしてヒルムシロ科のエゾヤナギモという水草は、Potamogeton caule compresso, folio Graminis canini……という長たらしい名前から、簡潔なPotamogeton compressumになり、私たち現世人類は「知恵のあるヒト」という意味のHomo sapiensと呼ばれるようになった。
出典:特集:リンネ 植物にかけた情熱の人/p2-3
リンネは百年以上前に考案された二名法を動植物全てに一貫して採用した。ただ採用しただけでなく、リンネは「属名と種小名」という組み合わせの命名法を考案した*3。
これらの分類と二名法の考案が現代の分類学の創始となる。よってカール・リンネは植物学の祖あるいは植物学の父と呼ばれる。
しかしリンネは近代学問の学者ではなかった。
リンネにはもっと深遠な目的もあった。植物を分類する「自然法則」を見つけることで、神が生物を創造した摂理を解明できると考えていた。
出典:特集:リンネ 植物にかけた情熱の人/p3