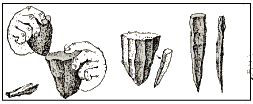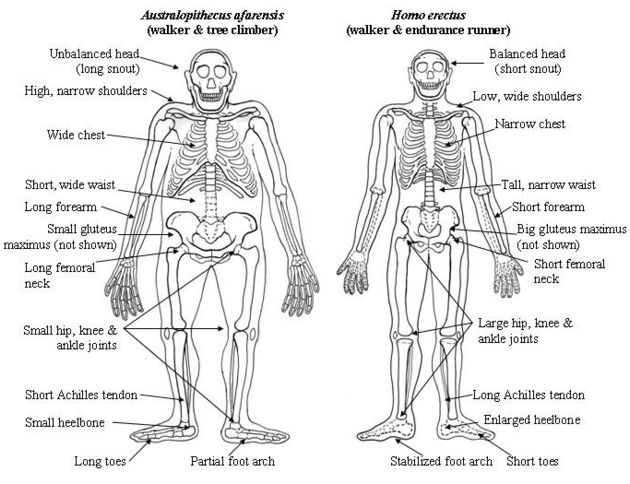(前回からの続き)
今回はホモ属と石器について書こうと思ったが、石器時代のほぼ全てがホモ属の時代だということを書き始めてしばらく経ってから気づいた。ここではとりあえず、打製石器の発展の話を書くことにした。
ホモ属と石器について
ホモ属が誕生したのは、一番早い説で280万年前*1。
最古の石器文化と言われているのはオルドワン石器(Oldowan)の260万年前(または250万年前)。この前に、330万年前の「ロメクウィアン文化」と名づけられている文化があったという説があるが、これを認めている人が少ないようだ*2 *3
ホモ・エレクトスは初め、オルドワン石器を使用していたが、180万年前にアシューリアン(アシュールAcheulean)石器を開発した。
打製石器の区分「モード論」
打製石器は数百年に亘る長い歴史を持つ。一言で打製石器と言っても多様な種類がある。
Grahame Clarkは1969年に出版した『World Prehistory 第2版』の中で、石器製作技術に基づいた進化段階によって打製石器を区分することを提案した。これを「モード論」と呼ぶ。
まずは5つのモード(様式)を書いておく。詳細はその後に書く。
- モード1(第1様式):チョッパー、チョッピング・トゥールと剥片を持つ石器群。
- モード2(第2様式):両面加工のハンドアックスを持つ石器群。
- モード3(第3様式):調整した石核から得られる剥片石器。
- モード4(第4様式):二次調整のある石刃。
- モード5(第5様式):細石器。
以下詳細。
モード1。オルドワン型石器群(oldowan industry)
打製石器の中で、最初期の石器群。
オルドワン石器群はモード1の典型と言われている。
オルドワン石器群を開発したのは後期のアウストラロピテクスか初期のホモ属か、どの種かは確定していない。
オルドワン石器作り方は、手頃な大きさの自然石を別の石で打ち砕くだけ。鋭利になった部分を刃物として使用する。礫(つぶて)の石器だから礫石器(礫石器)と呼ばれる。
打ち欠いてできた剥片を使用する場合、剥片石器と呼ばれる。

出典:打製石器<世界史の窓
出典:左:Oldowan<wikipedia英語版*4
右:Chopper (archaeology)<wikipedia英語版*5
- 左:石の一方を打ち砕いて鋭利な部分を作っている。
右:チョッパーと言われるもの。石の一方を打ち欠いて刃物として使用する。
ちなみに、石の両側を打ち欠いて刃を形成した石器は「チョッピング・トゥール」と呼ばれる。
剥片石器の代表的なものはスクレイパーというものがある。木を削ったり皮を切ったり(サイドスクレイパー)、皮の脂肪を掻き取ったりする(エンドスクレイパー)道具*6。
『人体』にオルドワン石器についての言及があるので引用しよう。
私たちの平たい歯では固い肉の繊維を噛み切れないので、ひたすら噛みつづけなければならない。[中略]最初の狩猟採集民が類人猿と同じような食べ方で、生の未加工の食物だけをずっとくちゃくちゃ噛んでいたなら、それに時間をとられすぎて狩猟採集などやっていられなかったはずなのだ。
この問題の解決策が、食物の加工だった。といっても、最初はごく単純な技術が使われていただけだ。実際、最も古い時代の石器はあまりにも原始的で、一見すると道具とは気づかないようなものもある。これらは総称してオルドワン石器と(タンザニアのオルドヴァイ渓谷にちなんで)呼ばれ、粒子の細かい石の一端を別の石で打ち欠いて作ったものだ。大半はタダの尖った石の剥片だが、なかには長いナイフ状の刃がついた、チョッピングツールと呼ばれる切断用の石器もある。このような古代の遺物は、いまの私たちが使っている洗練された道具にははるかに及ばないが、それでもチンパンジーにはとうてい作れないものであり、単純な構造だからといってその重要性が減じるものでは決してない。これらはじつに鋭利で、何にでも使える万能型の道具なのだ。[中略]
ヤギの生肉を噛み切るのは容易ではないが、あらかじめ小さく刻んでおけば格段に噛みやすくなり、消化もらくになる。食糧加工は植物性食物にも魔法のような力を発揮する。最も単純な加工法は、細胞壁などの消化しにくい食物繊維を分断することで、それによってどんなに固い植物も噛みやすくなる。また、石器を使って塊茎や肉片などの生の食物を切ったり叩いたりするだけで一口ごとのカロリー摂取量もぐっと増加する。口に入れる前に小さくしておいた食物は、消化の効率が断然いいからだ。実際、最古の石器についての研究から、肉を切るのに使われていた石器は一部であって、大半は植物を切るのに使われていたことがわかっているが、それもあながち意外ではないだろう。人間は、少なくとも狩猟採集をはじめたときからずっと食糧を加工してきたのだ。
出典:ダニエル・E・リーバーマン/人体 600万年史 上/早川書房/2015(原著の出版は2013年)/123-124
モード2。アシューリアン(アシュレアン、アシュール)石器群(Acheulean industry)
両面加工のハンドアックスが特徴。

出典:Acheulean<wikipedia英語版*7
- 上の写真は一つの石器の表・裏面と側面を表している。
この石器を開発したのはホモ・エレクトスと言われる。開発時期は175万年前より前(180万年前?)とされる((ケニア、トゥルカナ湖西岸で世界最古のアシューリアン、ハンドアックス見つかる<河合信和のブログ 2011/9/11))。
アシューリアン(アシュール型)石器とは何か?
アシューリアン石器とは,「ハンドアックス」などで代表される大型の打製石器をさす.「ハンドアックス」は「握り斧」とも呼ばれ,丸まった斧頭(楕円から丸まった三角形)の形をしており,典型的なものは最大長15~20cmの大きさである.多くは,石器の両面が加工されているため,「バイ・フェイス」(両面加工石器)とも呼ばれる.
ハンドアックスや他の両面加工の大型石器は,人類が初めて,形を予め意識して加工・製作した道具(石器)と見なされている.初期アシューリアン石器は,従来から,アフリカのホモ・エレクトス(原人)の時代に,150万年前ごろ以後から発見されてきた.アシューリアン石器は,ホモ・エレクトスの後継のホモ・ハイデルベルゲンシス(旧人段階の古人類の一種)の時代からも数多く発見されており,約20~30万年前まで作製されていた.
出典:最古のアシューリアン石器(論文解説資料、2013年1月) <東京大学総合研究博物館 人類形態研究室(諏訪研究室)
- ハンドアックスの他にはクリーヴァ(cleaver 肉切り包丁)、ピック(pick)*8も代表例。

出典:打製石器<世界史の窓
- ハンドアックス(バイフェイス)の作り方・使い方
- 上のような手のひらに収まるサイズの石器は後期のものらしい。初期の石器は10cmとか16cmとか大きめのものらしい*9 *10。
前述の『人体』にはアシューリアン石器群は「少しばかり洗練され」たと書いてあるが(p161)、
アシューリアン石器群についての一般的理解は、前期ではストーンハンマーによる粗い両面加工が特徴的な大形石器であるのに対して、後期は軟質ハンマーによる精巧な加工が器体の全面に及び、左右均整で薄手に仕上げられ、小形化するなど、アシューリアン石器群の技術・形態に進展傾向が認められる。この技術的進展について、安斎がクラークの見解を紹介している。それによると、ハンドアックス、クリーヴァーなどの両面加工石器は「必要に応じて均整の取れた対称的な平面形と両凸ないし平凸形の断面に仕上げられている。石材が礫の形で存在するところでは,両石器の製作は直接打法による礫のリダクション-小型化・変形化-過程をとる。後期アシュレアンではさらに技術的発展をみる中部更新世後期までに,特に両面加工石器の素材となる大型剥片を剥離する調整石核のさまざまな剥離技術-.........-を生み出していた」(安斎 2003、93p)。
出典:橘 昌信(研究分担者 : 別府大学文学部・教授)/タムネ遺跡のアシューリアン石器群と東アジアのハンドアックス石器群/セム系部族社会の形成 - 国士舘大学 平成19年度研究報告
技術の段階的な発展ではなく、同じ技術の中の改良がなされている。小型化すれば持ち運びに便利で、女性でも簡単に扱えるだろう。
ここでホモ・エレクトスの生活風景が感じられる遺跡の発見のニュースの一部を引用しよう。
[イスラエル北部にあるゲシャー・ベノット・ヤーコブ遺跡]は75万年前の狩猟採集民の野営地で、ホモ・エレクトスなどの人類の祖先によって作られたと考えられる。現代人であるホモ・サピエンスが出現したのは25万年前にすぎないことが化石記録からわかっている。
この遺跡では、握斧、両刃の礫器(チョッピングツール)、削器、ハンマー、突き錐といった人工物や、動物の骨、植物の残骸が、それぞれ別の場所に埋まっていた。
出典:現代的生活の起源はホモ・エレクトスか<ナショナル・ジオグラフィック日本語版 ニュース 2010.01.12
この遺跡では火の使用の証拠もある。現代の狩猟採集民の生活に近い風景が想定されているのだろう。
「Acheulean<wikipedia英語版」によれば、アシューリアン石器群は10万年前まで続いた。
モード3。石核調整技法(Prepared-core technique )
上の引用にあるようにアシューリアン石器群の発達の中から大型の剥片の石器を作る技術が生まれる。これを石核調整技法という。
アシューリアン石器群のハンドアックスは、大きめの石(素材)から剥片を打ち欠いて作る。剥片を使うこともあるが、基本的に剥片はゴミ。
これに対して石核調整技法は、剥片こそが石器で、残された素材はゴミとなる。
- 素材を石核と呼ぶ。
- 剥片の石器を剥片石器と呼び、ハンドアックスのように石核を使う石器を石核石器と呼ぶ。
石核調整技法の代表はルヴァロワ技法(Levallois technique)と呼ばれるもので、アフリカ、西アジア、ヨーロッパで用いられた。時期については「Levallois technique<wikipedia英語版」で一番早いのがアルメニアの335,000年前。この記事の中で、Adler氏によれば、この技術は各地でアシューリアン石器群を作る作成法から独自に興った、と主張している。この技法の終焉も各地で違うのだろう(時期は全く分からない)。
ルヴァロワ技法による石器の作り方がyoutube動画で見ることができる。
Lasca levallois - youtube
- 上の動画では出来上がった石器を竹の裂け目に差し込んで、柄のある斧にしているが、ルヴァロワ技法ができた初期はハンドアックスとして使ったのだろう。
- 動画を見て分かるように、この技術は経験と高い技能を要する。出来上がった石器を想定しながら、刃先となる部分を打ち欠いて、最後に素材と剥片を打ち分ける(上の動画と「Levallois technique<wikipedia英語版」のgifも参照)。
- 出来上がった石器はアシューリアンの石器(両面加工石器)よりも薄くて軽くて鋭利だ。
- ただしこの技術を用いる場合は石質が限られる。
ルヴァロワ技法と関係があるかどうか分からないが、50万年前の剥片石器が南アフリカのカサパン(Kathu Pan)から発見された、という発表があった(人類は石槍を50万年前から使用?<ナショナル・ジオグラフィックニュース2012.11.19)。ただし、当然のことだが、「50万年」という数字や研究チームの仮説が全面的に受け入れられるためには、別の発掘とさらなる研究が必要だと研究チームも認めている。
『人体』では彼らの仮説を受け入れて、50万年前に剥片石器技術と、上の記事には書いてないが、槍を投げて狩りをした、と書いている(p161-162)。
モード4。石刃技法
石刃
英語でブレード blade,フランス語でラーム lameともいう。円錐状石刃核の打面を周縁に沿って打撃し,側面から次々に打剥された剥片石器で,後期旧石器時代を特徴づけている。基本的には両側平行の長方形で,長さが幅の2倍をこえるもの。石刃の両側は鋭利な刃をもつが,片側を刃つぶしすればナイフ,一端をとがらせると尖頭器あるいは錐,端部に加工するとエンド・スクレーパー,特殊な加工を加えるとグレーバーなど,用途に応じた多様な石器に仕上げられる。
出典:石刃<ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典<コトバンク
上の引用で石刃とその種類と石刃技法が簡潔に書かれている。
- 「円錐状石刃核」は正確に言えば「多角錐状石刃核」。平面は十角形とか十五角形など角の数が多い。
- 『人体』など他の人の説明では「プリズム状(の)石核」と書いている。プリズム(prism)は角柱の意味。角錐から剥片石器を作るか、角柱から作るかの違いはあるが、それ以外は同じ。
この技術の代表例はオーリナシアン(オーリニャック文化)(後期旧石器時代、45000~、または、42000~)。担い手はホモ・サピエンスとのこと。これより前の石刃技法については分からない。
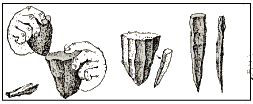
出典:打製石器<世界史の窓
- 上の引用ではこの絵は「剥片石器」の箇所にあったが、間違いである(すぐ下の「石刃技法」と勘違いしたか、単なるミスをしたのかもしれない)。
Blade Core Techniqueというyoutube動画も参照。
モード5。細石器(microliths)
細石器
長さ数 cm,幅 1cm前後の小型の石器。なかには長さが 1cmに満たないものもある。後期旧石器時代末に現れ,ことに中石器時代に盛行した。不定形な石器もみられるが,幾何学形細石器と呼ばれるものは,長方形,三角形,台形,半月形を呈している。これらは主としてアフラシア大陸西部に分布する。個々の石器は単独で用いられるものではなく,木または骨の柄の片側あるいは両側に縦に刻まれた溝へ数個ないし十数個がはめこまれ,ナイフ,鎌,あるいは槍,銛として使用された。刃部が損傷すれば,その部分だけをはめ替えればよい。
出典:細石器<ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典<コトバンク
使い方の一例が下の写真。

Flint microliths found at Mountsandel, some mounted into a modern wooden knife handle and an arrow. © National Museums Northern Ireland
出典:Mountsandel.com
上の写真はアイルランド出土の細石器だが、年代は分からない。複数の細石器を木や骨に嵌め込んで使用する。
細石器が出土する文化で代表的なものは、後期旧石器時代~中石器時代の西アジアのケバラ文化・ナトゥーフ文化、ヨーロッパのマドレーヌ文化あたり(記事「2万年前~(ケバラ文化/マドレーヌ文化)」と「定住型文化の誕生~ナトゥーフ文化」参照)。
細石器文化の一種に細石刃文化がある。
この文化はシベリア以東、中国、日本に伝わっている。
細石器文化と細石刃文化を峻別する定義は私には分からないが、ネット検索した感触では以下のような区別ができると思う。正答が分かれば書き直そう。
- 細石器文化=アフラシア大陸西部(環地中海東部)に繁栄して、幾何学的細石器を産んだ文化。
- 細石刃文化=シベリア以東、中国、日本に繁栄して、(幾何学的細石器を産まず)日本刀のような形の剥片石器を量産した文化。